NEWS & TOPICS
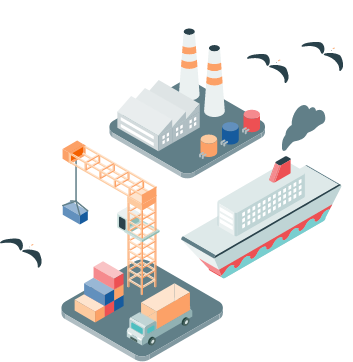
2025.10.05
「上司ガチャ」をなくす!部下が選ぶ上司選択制度のメリットと課題

「今の仕事は好きだけど、上司との相性がどうしても合わなくて…」
こんな風に悩んでいる、あるいは悩んだ経験がある人は少なくないでしょう。
実は、多くの企業が抱える「優秀な人材がすぐに辞めてしまう」という問題の裏側には、上司と部下のミスマッチが潜んでいます。
先日テレビの情報番組を観ていたら、とある企業の「上司選択制度」について紹介していました。この制度を利用して異動した社員、異動された上司、新たな異動先となった上司が、いずれも、顔と実名とともに出演していました。
とても興味をひかれたので、この記事では上司選択制度について深堀します。
なぜ今、「上司選択制度」?
離職の決定打は「人間関係」、特に上司との相性
企業はせっかく採用した若手社員に期待をかけますが、残念ながら短期間で退職してしまうケースは後を絶ちません。
退職理由を詳しく見てみると、「仕事内容が不満」というよりも、「人間関係」や「直属の上司との相性」が決定打になっていることが非常に多いのです。
特に、価値観やマネジメントスタイル(組織やチームを動かす「やり方」の傾向)が合わない上司の下では、部下のストレスは溜まる一方です。これが、社員の定着を阻む大きな壁になっています。
共感を呼ぶ「上司ガチャ」という言葉

SNSなどでよく見かけるようになった「上司ガチャ(上司くじ)」という言葉をご存知でしょうか?
これは、まるでカプセルトイのように、配属や異動でどんな上司に当たるか「運任せ」だという、働き手の不満と無力感を象徴した表現です。
「期待通りの上司なら”当たり”、そうでなければ”外れ”」という感覚は、多くの働く人の共感を呼んでいます。
つまり、「誰の下で働くか」が、その人のキャリアや仕事の満足度を大きく左右する時代なのです。
こうした社会的背景のもと、「この”上司ガチャ”を意図的にやめよう」という発想から生まれたのが、今回ご紹介する「上司選択制度」です。
上司選択制度とは部下が上司を選ぶ仕組み
上司選択制度とは、社員(部下)が、自分の直属の上司をある程度、指名・選択できるようにする仕組みのことです。
これは、従来の「会社や人事が上司を一方的に決める」という仕組みを反転させ、「部下が自分の上司を選べる権利を持つ」という、非常に革新的な人事制度と言えます。
制度の大きな目的は、上司と部下のミスマッチを防ぎ、社員のエンゲージメント向上や離職防止、そして成長支援を図る点にあります。
導入企業事例:離職率が劇的に低下した企業

実際に「上司選択制度」を導入している企業に、さくら構造株式会社があります。
同社では、社員が年に一度、アンケート形式で希望する上司(班長)を第2希望まで選び、それを基に人事異動を行う方式を導入しています。
同社の離職率は2018年に11.3%でしたが、2022年にこの制度導入すると、翌2023年には0.9%に低下しました。(参照記事:さくら構造株式会社URL「朝日新聞9/8号で「上司選択制度」が取り上げられました。」)
また、興味深いのは、上司側にも変化があったことです。「自分を選んでくれた部下のために、より丁寧に育てよう」という意識が芽生え、結果的に管理職の質の向上にもつながっています。
中には、幹部ポジションを社員の投票で決める「総選挙型」を組み合わせ、組織全体に透明性と柔軟性を持たせようとしている企業もあります。
選択制度が会社と社員にもたらすメリットと注意点
上司選択制度は、社員だけでなく、企業側にも大きな影響を与える一方で、運用上の難しさも存在します。
【メリット】企業成長のエンジンになる側面
離職率の劇的な改善
上司とのミスマッチによる離職が抑えられるので、人材の定着に直結します。
上司のマネジメント力向上

「選ばれる上司」でいるためには、部下を育てる力、話し合う力、そして信頼を築く力が欠かせません。
「選ばれなければ組織を維持できない」というプレッシャーが、管理職の成長を後押しする強い動機づけになるのです。
社員の主体性の醸成
上司を選ぶという行為は、「自分はどう成長したいか」「どんなスキルを身につけたいか」を深く考えるきっかけになります。
社員のキャリア志向と仕事が結びつきやすくなるのです。
【注意点と落とし穴】制度を失敗させないための壁
「人気投票」化のリスク
表面的に「優しい」「厳しくない」上司に希望が集中し、「強みはあるが、厳しく指導する」タイプの上司が敬遠される可能性があります。
これでは、組織のバランスが崩れ、必要な指導力が育たなくなるかもしれません。
選ばれなかった上司のモチベーション
候補上司の中で、誰からも選ばれなかった人がモチベーションを維持するのは簡単ではありません。
会社として、彼らへの適切なフォローアップや動機づけをどう設計するかが重要な課題となります。
運用コストの増加
希望の集約、人員の調整、組織のバランスを保つための仕組み作りには、人事部の手間や人員(コスト)がかかります。制度が煩雑になりすぎると、本末転倒です。
制度導入を成功させるための4つの鍵

導入を成功させるには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
1. 上司評価制度との「連動設計」
単に「選ぶ」だけで終わらせず、上司の評価制度と連動させることが重要です。
たとえば、「部下満足度」を上司の成績を測る要素の一つに組み込むなど、選ばれるために努力したことが報われる仕組みが必要です。
こうすることで、制度が「ただの人気投票」になるのを防ぎ、社員にとって信用できる公正な仕組みとして機能するようになります。
2. 組織規模と上司数のバランス
上司の選択肢があまりにも少ないと、結局は「選べない」のと同じです。 組織規模に対し、適切な数の候補上司がいることが、「上司を選ぶ」制度の成果が出るかどうかを決めます。
3. 選べる範囲とルールの明確化
組織運営に必要な社員の希望(上司選択)と、会社が計画している定期的な人事異動をどう両立させるかをあらかじめ決めておく必要があります。
そのため「同部門内のみ」「同じレベルのポジションの範囲内のみ」など、選択できる範囲を制限しましょう。
4. なんでも話せる社内の雰囲気を作る
最も大切になるのは、社員が本音で話せる社内文化を築くことです。
もし、上司や同僚に対し「希望を言ったら角が立つのでは?」「もし通らなくても、その上司の下で働くのが気まずい」という萎縮した空気が残っていては、せっかくの制度も形だけで実効性の無いものになってしまいます。
誰もが「正直な気持ちを伝えても、評価や人間関係に悪影響が出ない」と心から信じられる社内の雰囲気が、制度を成功させるための何よりも重要な土台となります。
この記事の最初で書いた、実際に「上司選択制度」を活用して異動した社員さん、今では元の上司のもとに再異動し、良好な信頼関係が築けているとのことです。
参照元:TBS「THE TIME,」で「上司選択制度」が取り上げられました。
上司選択制度を「定着の柱」にするために

上司選択制度は、社員が気持ちよく働けるようになり、結果として会社に長く留まってくれるという点で、とても魅力的なアイデアです。
しかし、この仕組みを成功させるには、穴のない、しっかり考え抜かれた制度が必要です。また、職場の文化、つまり「うちの会社に合っているか?」という点も大切です。
この制度を一時的な取り組みで終わらせず、キャリア支援や評価の仕組みとワンセットで動かすことで、社員は「会社が本気で自分たちを大切にしている」と感じられるはずです。そうすれば、制度は確実に力を発揮します。
社員が「この会社は自分を大切にしてくれている」と感じるには、人事制度のような大きな仕組みだけでなく、毎日の職場の「快適さ」も欠かせません。
社員の満足度を「毎日の食事」から高めてみませんか?
エムピーアイは、社員食堂の提供を通じて企業の健全運営をお手伝いしております。
お問い合わせはこちらから
施設内に売店や社員食堂設置を
ご検討中の方へ
まずはお気軽にご相談ください
